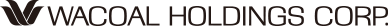コーポレート・ガバナンスの実効性強化の取り組み
当社は「ステークホルダーからの信頼感の向上(社会的価値創造)」と「組織のパフォーマンス向上(企業価値向上)」という2つの観点から、毎年、取締役会の実効性について評価を行い、継続的に取締役会の機能を高め実効性を向上するべく努めています。評価によって抽出された課題に対する改善施策に取り組み、次の事業年度の取締役会評価の際に改善状況を確認すると同時に、現状の課題を確かめる運用を継続しています。
評価プロセス
2022年3月期から、第三者機関の評価設計を活用(アンケート調査内容作成・分析・他社比較・課題抽出・アクションプラン起案など)した取締役会の実効性分析・評価手法に変更しています。
第三者機関の評価設計を活用したアンケート調査とインタビュー結果に基づく分析・評価は隔年実施とし、そのインターバル年度においては、アンケート調査から抽出された課題を改善する取り組みに注力すると同時に、独立社外役員会議でのモニタリングや意見収集を通して評価を行っています。
当事業年度(2025年3月期)の実効性評価では、前事業年度に抽出された課題に対する改善対応の取り組み状況を重視した評価設計の更新を行い、「2023年3月期及び2024年3月期の実効性評価の結果により挙げられた課題に対する、当事業年度での改善対応状況」を確認しました。
取締役及び監査役全員を対象に、独立社外役員会議事務局によるアンケート調査を行い、アンケートの回答内容やフリーコメントに記された課題意識の深掘り等に加えて、今後の取締役の役割・責務と、これからの取締役会の実効性向上のための更なる改善策についての意見聴取を実施しました。
その後、改善策については、独立社外役員会議で忌憚のない意見を取り交わし、取締役会に答申しています。
実効性の評価結果と改善に向けた取り組みの状況
アンケート調査への回答を踏まえて取締役会で審議した結果、当社の取締役会は概ね適切に機能し、実効性が確保できている旨を確認しています。
実効性が確保できていると確認した理由は次のとおりです。
- 事業視察や、執行役員及びブランドマネージャーをはじめとする従業員との交流機会を設ける等、社外取締役及び社外監査役が、取締役会外の活動によって当社の事業を理解する取り組みを継続的に行っており、それに基づいた質の高い議論がされていること
- 社外取締役が過半数を占める取締役会において、社外の知見や経営経験を活かした自由闊達な議論が実施されていること
- 中期経営計画(リバイズ)における主要な経営課題に対する取り組み進捗について、定期的に報告がなされ深度ある議論が行われていること
- 前事業年度の実効性評価で挙げられた課題に対する改善活動が一定程度進んでいること
実効性の評価結果と改善に向けた取り組みの状況
| 評価結果(課題・指摘事項) | 改善に向けた取り組みの状況・計画 | |
|---|---|---|
| 当事業年度 (2025年3月期) 評価結果は過年度の指摘事項 |
|
(取り組み状況) (計画) |
|
(取り組み状況) (計画) |
|
|
(取り組み状況) (計画) |
|
|
(取り組み状況) (計画) |
|
|
(取り組み状況) (計画) |
|
|
(取り組み状況) (計画) 以上の取り組みと併せて、社外取締役の知見を一層活用しながら、取締役会の監督・助言機能をさらに強化する計画 |
コーポレート・ガバナンスに関する取り組みの変遷
| 1977年 | ADR(米国預託証券)発行* | 日本企業としては8番目にADRを発行。発行に察しては、米国証券取引委員会(SEC)から連結決算書の作成をはじめ、米国会計基準での会計報告が求められる。 |
|---|---|---|
| 2002年 | 執行役員制度の導入と取締役数の減員 → 取締役数:13名 → 9名 |
権限の委譲と責任体制の明確化を図り、適正かつ効率的な体制の構築を目指し2002年6月に執行役員制度を導入、同時に取締役を減員。 |
| 2005年 | 純粋持株会社へ移行 | グループ全体の戦略的な意思決定や最適な資源配分を効果的に行い、傘下の事業会社の責任と権限を明確にして機動的な業務執行を行うため、持株会社体制へ移行。 |
| 社外役員の増員 | 取締役会と監査役会の一層の公正性、独立性を目指し、社外取締役2名、社外監査役1名を増員。 | |
| 2007年 | 役員人事報酬諮問委員会を設置 → 委員会の員数:4名(社外取締役含む) |
取締役や執行役員に対する指名・昇格・報酬については、管理担当取締役を委員長として社外取締役をメンバーに含む役員人事報酬諮問委員会を設置。 |
| 2010年 | 全社外役員を独立役員として届出 → 独立役員としての届出:6名 |
社外取締役と社外監査役の全役員について、東京証券取引所に対し独立役員としての届けを行う。 |
| 2015年 | 独立社外役員会議を設置 | コーポレート・ガバナンスや取締役会の運営改善に関する議論、内部監査等の情報共有を図る独立社外役員をメンバーとする独立社外役員会議を設置。 |
| 2018年 | 役員指名諮問委員会及び役員報酬諮問委員会を設置 | 2007年に設置した役員人事報酬諮問委員会を変更。 |
| 2021年 | 譲渡制限付株式報酬制度の導入 | 取締役(社外取締役を除く)に、株価変動のリスクを株主の皆さまと共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、株式報酬型ストックオプションを廃止し、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入。 |
| 2022年 | 基本報酬および株式報酬の比率を変更 | 役員報酬は「基本報酬」「業績賞与」「譲渡制限付株式報酬」によって構成。「基本報酬」「譲渡制限付株式報酬」の比率を見直し、上位者ほど株式報酬の割合が高い構成に変更。 |
| 2024年 | 業績連動型譲渡制限付株式報酬の導入 | 取締役(社外取締役を除く)に対して、報酬と会社業績及び当社の株式価値との連動性をより明確化し、当社の企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、業績連動型譲渡制限株式報酬制度を導入。 |
* 2013年には米国NASDAQ市場におけるADRの上場を廃止、同時にSECの登録も廃止。